トップメッセージ
INVESTOR RELATIONS
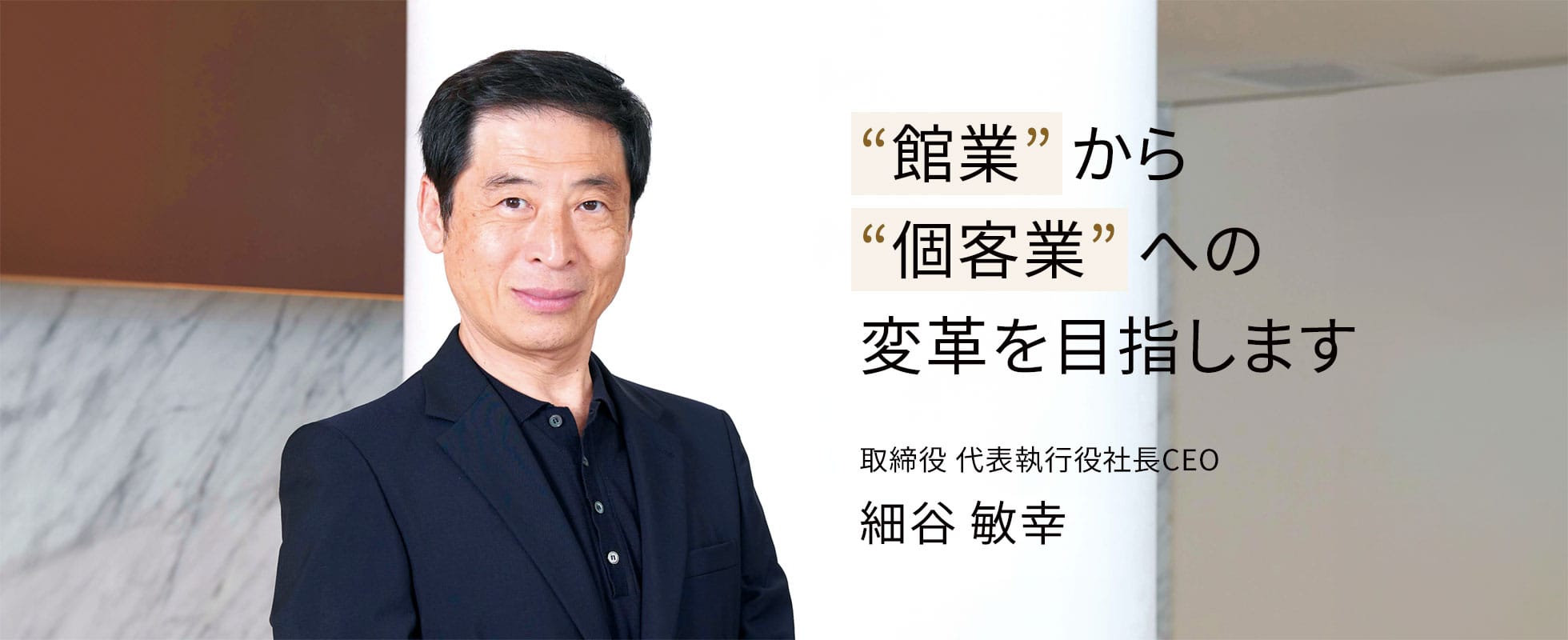
これまでも、これからも、私たちは挑戦を続けます
好調に推移する当社の「百貨店の再生」
コロナ禍を経た百貨店を取り巻く環境
代表執行役社長CEOの細谷敏幸です。2024年の今、当社を含めた百貨店業界各社は苦しかったコロナ禍を経て、活況にあります。これは、百貨店を取り巻く環境が大きく変化したことがプラスに働いていると考えています。一つはリオープンで、昨年5月に新型コロナウィルス感染症の位置づけが5類へ移行したことで、それ以降の人流が大きく変わりました。それによって当社のようにリアルの場をきちんと持っているところはお客さまが私たちの情報を受け取ってくださり、販売員と会話しながらお買い物を楽しんでいただく、という店頭の動きが2024年度戻ってきたことを実感します。
またデフレ現象の改善もとても大きいと思います。デフレが30年余りも続いたため、諸外国に比べ物価が安定して見えた日本でも、いよいよあらゆる商品の価格が、歴史的な円安とも重なって急激に上昇しています。もちろん、価格上昇に伴って売上も上がるわけですが、特に百貨店にあるようなこだわった商品、高価格帯の商品などは、「今買わないと次に来るときは値段が上がってしまうかもしれない」という気持ちがお客さまの背中をそっと押してくれる、ということも十分考えられます。
インバウンドも大きな要因です。訪日外国人の入国数は年々増加し、政府発表によると6月には単月で313万人と過去最高を記録したとのことです。このインバウンドのお客さまにとっては価格改定より円安効果の方がはるかに勝っていて、百貨店でも大変多くのお買い物をいただいていることが各社の発表からも読み取れます。さらに国内の富裕層の増加も見逃せない要因です。複数のシンクタンクが出しているデータを見ると、金融資産を1億円以上保有する富裕層はこの10年で3割近く増え、保有する資産は100兆円も増えている、今後も増加するだろう、とのことです。これは株高の影響が一番大きいといわれていますが、我々はこういう情報を見逃してはならないとあらためて思います。
当社の百貨店事業の再生の進捗
翻って当社の状況ですが、2022年度~24年度の3ヶ年計画では「百貨店の再生」を大きく掲げています。スタート当初の目標は、24年度に過去最高営業利益350億円、長期的には30年度に500億円達成にチャレンジしよう、というものでした。始めてみると初年度から大変順調に進み、2年目の23年度には543億円となって10年後の目標を早くもクリア、最終年度となる今期24年度では720億円を見込み(24年8月時点)、過去最高を更新し続けています。
また、増益の中身も以前とは大きく変化しました。増益の手段を増収と経費構造改革の両面で進めているため、百貨店業として長年の課題であった営業利益率は総額売上高比率で5%超、売上高比率では12%を超えています。それにつれて最終利益もしっかりコントロールし、これも大きな課題であった資本効率も改善が進み、5%超が目標だったROEは23年に続き24年度も9%を超える見通しです。店舗で象徴的なのは伊勢丹新宿本店の売上高です。過去にはバブル期に一度3,000億円を超えたことがあるだけでしたが、23年度に3,758億円、24年度は4,110億円と初めて4,000億円を超える見通しです。世界を見渡しても、この面積でこの売上規模の店舗はほかに無いでしょう。
こうした当初計画を大きく上回る好業績の要因として、中期計画がスタートした22年当時は先に述べたような大きな環境変化を予測できませんので、外的要因が大きなドライブになっていることは間違いありません。しかし、中身をよく分析していくと、必ずしも外的要因だけでなく、当社独自の戦略の推進=ビジネスモデルの変革が大きな要因になっていることが分かります。
「百貨店の再生」のひみつ
私たちが目指す姿
ではそのビジネスモデルの変革とは何か、その前に、「百貨店の再生」を含めた当社の中長期計画をつくった背景について、少しお話させてください。当社の創業は古く、1673年日本橋で始まりました。350年以上続いているわけですが、創業から約200年後、1904年に大きなエポックがありました。これが「デパートメントストア宣言」、三越の設立です。それまでずっと、「呉服」という1アイテムだった事業は、200年を経て「百貨」という100アイテムに変化した、このビジネスモデルの転換が、今も私たちを支えていると思います。
しかしながら現代では日本全体の消費マーケット規模は変わらないのに、この50年ほどで多くの小売業が参入してきました。例えば、コンビニエンスストアは50年前に、郊外型のショッピングセンター、アウトレット、さらにはEC、外資も含めたこれらの新しい業態が日本の小売の世界へ次々に参入し、存在感を増してきています。一方で百貨店はその間、殆ど変わらなかった、進化してこなかったと思います。その結果どうなったかというと、1991年に約10兆円あった百貨店業界の売上が、今や約5兆円と半分になってしまいました。
三越は351年、伊勢丹も138年の長い歴史を持ちますが、どちらも創業以来「お客さま第一」を掲げ、時代や社会の変化、環境の変化に対応しながらご要望を先取りし、提案して今日まで続いてきました。その中で私たちは、長く培ってきた強みを持っています。三越伊勢丹グループの強みは、お客さまに認められた「のれん」の価値であり、長い歴史の中で大切にしてきた個客基盤そのものです。三越「のれん」の強みとは、お客さま第一の企業文化から生まれてきた「おもてなし」の力、お一人お一人のお客さまのご要望に徹底的にお応えする接客力にあります。一方、伊勢丹「のれん」の強みとは、三越同様にお客さま第一の企業文化のもと、多くのお客さまにご来店いただき、魅了し続ける店舗を、ものづくりまで手掛けるチャレンジ精神で高めてきたマーチャンダイジング力です。しかし三越と伊勢丹が統合して15年以上ですが、せっかくのこの両者の強みを掛け合わせ、十分に生かしきれているとはまだいえません。これを何とか変えていきたい、そうしてつくったのが当社の中長期計画です。
そこであらためて原点に立ち返り、「お客さまのお困りごとを感動的に解決し、ニーズに対し革新的に提案する」ことで、お客さまの暮らしを豊かにする“特別な”百貨店を中核とした小売グループ、を「私たちが目指す姿(ビジョン)」として、2021年に中長期計画の発表にあたって掲げました。その後、このビジョンの実現に向け、「私たちの存在意義(ミッション)」と、「私たちが大切にする思考と行動(バリューズ)」を明確化し、2023年5月に新たな三越伊勢丹グループの企業理念として再整理しています。再整理のプロセスでは、グループ従業員、経営陣全員が一年かけて話し合いながらまとめていく、という特徴的なものでした。従業員たちにとってグループ全体で目指すものが明確にあって、いつもよりどころになるもの、迷ったときに立ち返れるものが整ったことが、みんなの心持ちに少なからず影響を与えていることも、この計画が順調に進んでいる要因の一つだと考えています。
ビジネスモデルの変革~「マスから個へ」
私たちがビジネスモデル変革のポイントとしたキーワードは「マスから個へ」、です。従来の百貨店は家族や友達と出かけていく場所で、ひとたび館に入れば自由気ままに店内を回りながらお買い物したり、お食事したりと長い時間滞在する場所でした。ですから我々も、広域から大勢のお客さまを集める=マスマーケティングのビジネスモデルさえやっていれば十分でした。館に呼び込みさえすれば終わり、つまり“館業”といえると思います。
しかし時代とともにお客さまの価値観や生活スタイルが変わり、先ほどお話ししたように商環境も大きく変わり、消費行動は大変成熟していきました。急速なデジタル化も加わり、お客さまはスマートフォンによって我々も追いつかないほど多くの情報から欲しいものを瞬時に検索され、必要なものだけお買い物し、すぐに帰られてしまいます。お一人お一人が、こだわりがある消費には徹底的にこだわる半面、そうでないものには機能と価格のバランスに大変シビアになる、というお買い物には、従来のマスマーケティングでは到底対応できません。
だから、「マスから個へ」の考え方が必要になります。一律対応のマスマーケティングから一刻も早く「個のマーケティング」へシフトし、お一人お一人のご要望に対応することです。初めてご来店されたときは「マス」顧客でも、ひとたびそこでお買い上げいただき、サービスを受けていただいたら、もう私たちのお客さま=「個客」としてずっとお付き合いしていく、お一人お一人の買い方をしっかりと考えながら、ひとの力で、時にはデジタルの力も借りて、そのお客さまにあたらしい提案をし続ける、だんだん当社のファンになっていただく、ファンの方をできるだけ増やしていく、そういうビジネスモデルへの変革です。私たちの強みである品揃えと編集力、提案力、サービス、すばらしい空間、持っている全てをしっかり生かしながらこの変革を実行すれば、シュリンクしてしまった百貨店を再生できるのではないか、それが私たちの中期計画です。
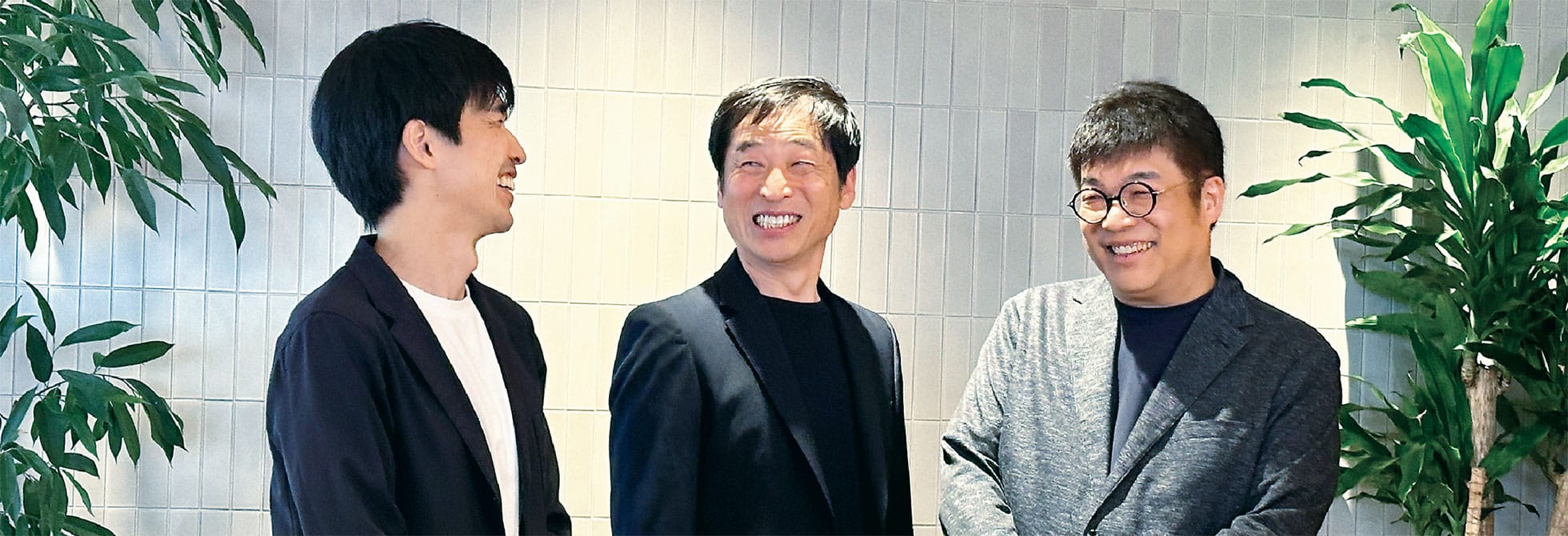
生活にこだわりを持ち、上質で豊かな生活を求める消費にお応えする~“高感度上質”戦略
では、具体的にどんなことを進めているか、戦略をご紹介します。まず一つ目は“高感度上質”戦略です。この高感度上質というのは、「顧客」の意味ではなく、「消費」の意味です。全てのお客さまは、どんな方にも、頻度は人それぞれでも、一生のうちに必ずある「こだわり消費」を私たちが逃さず対応することです。何かいいものが欲しいな、と思ったときに当グループののれんを使っていただける、「こだわり消費」=「“高感度上質”消費」のマーケットにおいて当社が圧倒的な存在感を発揮する、そんな状態をつくりたいのです。
そこでお伝えしたいのが、当社グループの総本山でもある、伊勢丹新宿本店と三越日本橋本店の両本店です。この2店をグループにおける「あこがれと共感の象徴」に進化させ、たまに行くなら伊勢丹に行きたい、三越に行きたい、と言っていただける存在を目指しています。例えば伊勢丹新宿本店は、“最先端のファッション”提案による世界ナンバーワン百貨店を目指し、品揃えは「本物・本質・こだわり・最先端」、といったキーワードに、「先行・限定」を掛け合わせ、新宿店にしか無い、付加価値の高いものを中心に展開する特別な環境で、最高のおもてなしを提供します。一方、三越日本橋本店は、「伝統・文化・芸術・暮らし」の強みをより一層磨き上げ、歳時記を大事にするお客さまの「上質な暮らし」のものが全て揃う店舗を目指しています。重要文化財としての中央ホール、三越劇場、店舗自体が伝統と文化そのものの特別な空間の中で、お客さまに上質なサービスとおもてなしを提供します。この両本店がお客さまのあこがれと共感の象徴となることで、グループ各店もそののれんのもとでつながり、一体となってお客さまと接していくことができます。これによりお客さまが、年に1回、ラグジュアリーブランドのバッグを買いたい、いい時計を買いたい、月に1回は品質の良い化粧品を買いたい、あるいは、大切な方にきちんとしたものを贈りたい、どなたにもあるそのようなときに当社の店舗を必ず選んでいただけるように、感度が高くハイタッチなサービスを提案します。そのため、全国各都市の店舗をそれぞれ母店とし、そこに小型店を衛星的につなげ、さらにデジタルでお客さまをサポートします。デジタルでつながっていると、グループ各店からでも伊勢丹新宿本店や三越日本橋本店の接客を受け、商品を選び、購入することもできます。こうしたつながりにより、日常は近くの店舗、ハレの日や特別なお買物は各都市の母店か、伊勢丹新宿本店や三越日本橋本店でも、といったことが全国各地で可能となり、当社のファンをより多く増やしていく原動力となる考えです。さらに、都心にある当社のもう一店舗の三越銀座店についてです。銀座四丁目の交差点、という世界でも唯一の場所にあり、売上高も24年度は1,100億円を超える計画で過去最高を更新し続けています。しかし、お客さまからはともすると三越日本橋本店の支店に見えてしまっていないだろうか、と思います。もっともっとあたらしい感度でグローバルな拠点にしていきたい、という考え方で、「世界の銀座を代表するニューコンセプトストア」として計画を策定中です。
また、“高感度上質”戦略においてもう一つの重要な要素は商品です。当社は単純にモノ、商品を売るだけではなく、モノを通して文化を売り続けたい、という考え方です。例えば、「サロンドパルファン」というプロモーションは、香りを身にまとう、香りを暮らしの中に取り入れる、という想いからスタートしたものです。「日本に香りの文化を提唱する」をコンセプトに2013年に初開催して以降、年々規模を拡大し大きな売上となっています。それだけでなく、そのファンの方々が集まったSNSでは、香水や香水文化について自由に発信しあって盛り上がっていく、というムーブメントまで起こっています。また、これも大きなプロモーションでご存じの方が多いかも知れませんが、「サロン・デュ・ショコラ」です。始まりは30年ほど前にパリで行われたチョコレートの祭典ですが、この本物を日本に何とか持っていきたい、ということで、単純にチョコレートのさまざまなブランドをかき集めるのではなく、本物のチョコレートとは何か、パティシエが考えるチョコレートとは何か、という信念のもとでやっています。こうした私たちの信念や情熱が、こだわりを持つけれどほかではなかなか満たされないお客さまの心をしっかりと捉えている、という例がいくつもあるのです。また別の視点では、世界中のラグジュアリーブランドとあたらしい組み方をしています。世界のラグジュアリーブランドたちはそのトップも含めて、私たち三越伊勢丹グループへ会いに来てくれたり、普段からコミュニケーションをとてもよく取ってくれます。なぜかというと、当社は多くの高感度上質な消費をするお客さまを持ち、外商という海外には無いお客さまとの特別な関係性を持てる接客手段を持ち、世界に名だたる店舗、という場所も持っているからです。この世界のラグジュアリーブランドと、いかに当社だけの特別な新しいものをつくり出せるのか、その結果、独自性のある商品やイベントがたくさん生まれてくるということです。
「マスから個へ」転換する仕組み~“個客とつながる”CRM戦略
こうした高感度上質消費を捉えることで集めたお客さまを、どうやって当社のお客さま=個客へしていくのか、その仕組みについてお話しします。私たちはお客さまのお買上げに従って差し上げるベネフィットをもっと適切にすることで、お客さまの当社に対するロイヤルティを高めていけると考えています。そのために当社がお客さまの顔が見え、つながった状態の方(識別個客)に、きめ細かなサービス提供や商品提案を行い、お一人お一人のご要望にお応えする仕組みをつくりました。従来、当社が把握できたのは、グループが発行するエムアイカードを通した方法に限られていましたが、現金や一般のクレジットカードをお使いの方でも三越伊勢丹アプリやデジタルIDを持っていただくことができるようになりました。さらに、この三越伊勢丹アプリ会員のお客さまやデジタルIDを持つお客さまが、お買上げによるベネフィットの違いに価値を感じていただけると、将来的にはエムアイカードを持っていただけるようになり、当社とより深くつながることができます。中期計画が前倒しで順調、とお話ししましたが、この三越伊勢丹アプリ会員の仕組みを新たに取り入れたことにより、“高感度上質”戦略と“個客とつながる”CRM戦略の両輪がとてもうまく回っていることを実感しています。エムアイカードだけが手段だった時には200万人ほどだった識別個客は今、三越伊勢丹アプリ会員、デジタル会員を合計して約700万人にもなっています。

すでに伊勢丹新宿本店や三越日本橋本店は、売上の70%が識別個客の方になっていますが、この識別化が進むとどうなるのか、単純に年間のお1人当たりの年間購買額が、非識別化のお客さまを1とすると、三越伊勢丹アプリに入ってデジタルで付き合っているお客さまは、そのだいたい2倍に、そこからエムアイカードを持っていただけると、さらに2倍になります。外商に入っていただくと、さらに3倍、と、どんどん上がっていくのです。なぜかというと、お客さまとの関係性がそれだけ深くなる、何を求めているのか分かる、それをしっかりとご提案できる、お客さまも当社を信頼して反応してくれる、こんな好循環がつくられるからだと認識しています。お客さまのニーズを伺っていると、時には百貨店で扱う商品以外のものもご提供する必要があります。以前はそのご要望にお応えできませんでしたが、この仕組みになってからはモノだけでなくコトも含めた「百貨店外MD(マーチャンダイジング=品揃え)」の提供も可能になっています。こうした一連の識別化の動き、ご提案の広がりは始まってまだ2年あまり、首都圏店舗中心の動きではありますが、今後地方店も進んでくると、さらに大きな効果が上げられます。“高感度上質”戦略によってお客さまは店頭やオンライン、三越伊勢丹アプリなどで私たちとつながります。加えてエムアイカードを持っていただくことでお買上げに従って適切なベネフィットを差し上げられるだけでなく、グループ外でのご利用や金融サービスのご提供など、さらにあらゆる場面で私たちとつながり続けることができます。“高感度上質”戦略と“個客とつながる”CRM戦略がしっかりと組み合っていくことで、「マスから個へ」と転換することができるのです。当社が目指す姿として掲げた「特別な」の意味は、こうした一連の考え方を表した表現です。世界にも発信できる、ナンバーワン、オンリーワンの百貨店。ナンバーワンは、商品もサービスも、一番のものを自信を持ってご提供できること。オンリーワンはお客さまに、三越でないと、伊勢丹でないとイヤだ、と言っていただけることです。「マスから個へ」とシフトする、お客さまお一人お一人のご要望をしっかり伺っていく、そうすることでお客さまのお悩みやお困りごとを感動的に解決し、関心ごとに対し革新的に提案していきます。
「百貨店の再生」のその先へ~“館業”から“個客業”へ
百貨店の強みをグループ全体の強みへ~“連邦”戦略
こうして百貨店事業の再生は順調に推移していますが、次にご紹介するのがこの“連邦”戦略です。当社は、グループ内に金融、システム、物流、建装、人材派遣などさまざまな会社が傘下にありますが、どのソリューションも大変特徴的で、建装事業では高級ホテルや国会議事堂の内装を請け負うなど、古くから業界内では知られた実力を持つ会社もあります。しかしこれまで、当社は百貨店事業の一本足打法のようになっていて、それ以外の各社はそれぞれが自分たちのノウハウと個別ルートの営業にとどまっていました。一例としてカード会社のエムアイカードはカード会員数約270万人の規模ですが、当社がつながっている700万人ものお客さまに対し金融事業としてのサービスを行うともっと発展拡大することが可能で、百貨店事業に偏っていたグループの利益ポートフォリオや収益力を大きく変える、埋蔵量の高い事業です。他の事業会社も同じで、百貨店の強みでつながった多くのお客さまに、百貨店以外の事業をグループのブランドのもとでご提案し、つながったお客さまのウォレットシェアを拡大、各事業の収益性を高めていくことができます。百貨店事業を再生し、こうした“連邦”戦略により各事業のビジネスモデルを構築した先には、百貨店を核とした「まちづくり」として、当社が全国の保有不動産の再開発だけでなく、サービス・コンテンツも、機能・インフラも自社で有機的に活用できるようになります。サービス・コンテンツとしては、オフィス、レジデンス、ホテルをはじめ、エンタメ、食、旅行が、そして機能・インフラとしては金融決済や内装、施設運営、システム、物流、人材派遣等々です。それぞれが当社ブランドのもとにサービスを展開していく状態は、「“特別な”百貨店を中核とした小売グループ」である当社だからこそ可能な、当社ならではの戦略だと考えています。
お客さまを中心に据えて、その方のことをよく分かっている当社が、その方が求めるあらゆるモノもコトも提案し、提供する、ライフスタイルをぐるっと取り囲む、それはもう百貨店業ではなく、“個客業”です。私たちはその変革を実現させたいと思っています。
“個客業”へ変わるチャンス

百貨店の事業モデルは時代に合わせて変革できず、硬直化しシュリンクしてしまった、と申し上げてきました。百貨店業界の各社の中には、もともとの「百貨店」という事業の将来性も考え、事業のポートフォリオをSC事業やデベロッパー事業に転換する動きが目立つようになっていることも事実です。しかし当社は百貨店の事業モデルを完全に転換し、「百貨店の再生」を実現し始めている手ごたえを感じています。それはお客さまをマスで捉え、館に集めればそれで終わりの“館業”から脱却したのであり、そこから百貨店を極めていよいよ“個客業”へ転換している、今はその過渡期のちょうど真っ只中にあります。
そのチャンスは大きく3つあると思っています。まず、「空間」です。百貨店が使っている土地建物、駐車場の上、事務所の上、百貨店以外何も使っていないこの状態を違う用途で使えないだろうか。百貨店を中核に置きながら、マンション、ホテル、オフィスやエンターテインメント、さまざまな用途を組み合わせることができたら、ここで収益化が図れます。次に「時間」です。百貨店は、朝10時から夜20時までしか営業していません。営業時間中、どんなに多くのお客さまでにぎわっていても、20時を越えると残りの14時間何もご提供できない。多くの組み合わせでまだまだ、お客さまともっと深くお付き合いする可能性があるのでは、ということです。さらには、「世界」です。日本のお客さまの識別化が約700万人と申し上げました。次は、今国内でうまく進んでいるのと同じことを、世界でやりたいと思います。インバウンドのお客さまのお買い物の中身を見ていくとコロナ禍前の化粧品のお買上げが中心だった時とは全く異なります。今は日本のお客さまと同じで、ラグジュアリーブランド、宝飾、時計、時には絵画などの美術品、いずれも、比較購買ができる、品揃えがほかとは違う、丁寧な提案が受けられる、安心できる、そういった理由で当社を選び、多額のお買い物をされています。今はこの方々と個でつながる手段がありませんが、国内でできているアプリを多言語化で開発し、識別化していく計画です。そうなってくるともうインバウンドという括りではなく、当社とつながっているお客さま、識別個客でどこどこの国にお住まいの方、ということになります。
こうした3つの可能性をしっかりビジネスモデルに取り込み、お客さまとのつながりを今よりももっと深く、もっと広く、もっと長くしていくことが、私たちが考える“個客業”の姿です。これが利益面でどんな変化をもたらすでしょうか。今はほぼ百貨店だけの利益ですが、それが三層の利益になっていきます。まずは百貨店を中核にしながら、保有する土地や建物の高層化、複合用途開発でホテルやマンションやエンタメをつくることで、一般的なデベロッパーとして得られる不動産の利益が加わります。さらに、その運営に関わるインフラが当社グループで賄えます。警備、清掃、内装、デジタル系のインフラ等々、全て“連邦”戦略で成長したグループ内の会社が行う利益が加わります。さらに最も大きいと思っているのは、これによって百貨店単独ではなく、魅力ある「まち」という面の吸引力が世界中からお客さまを呼び込み、ホテルもマンションもそれ以外も全て百貨店と連携させ送客すると、今の百貨店そのものの売上や利益がさらに増えると考えます。この三層の利益をイメージしながら“まち化”の投資をしていきたいと思います。
次期中期経営計画の基本骨子~“館業”から“個客業”への変革
2024年の11月には、いよいよ2025年度から始まる次の中期計画を発表していきますが、キーワードはまさに、“館業”から“個客業”への変革、ということです。その基本的な骨子をお話しします。次期中期経営計画は2025~30年度までの6ヶ年で、前半3ヶ年をフェーズⅠ、後半3ヶ年をフェーズⅡとする構成になっており、最終年度2030年度の営業利益は1,000億円の水準を考えています。フェーズⅡではいよいよ“まち化”着工・竣工時期が目線に入ってきますので、本格的に“まち化”の果実を刈り取っていく2031年度に向けて、この準備期間となる6年間の過ごし方が、その先の成長に向けて重要な期間になる、と考えています。
“個客業”としての価値提供の考え方について、この中期計画では具体的に百貨店以外の各事業も横並びでそれぞれの戦略やKPIを明確にしていきます。縦と横のマトリクスのイメージですが、縦が4つの事業、百貨店事業、金融事業、不動産事業、その他の関連事業です。それぞれは縦で、事業利益の拡大を図っていきます。一方、横の軸はお客さま、「個客」です。「個客」が百貨店でどうマネタイズされるか、それが不動産では、金融では、その他の事業ではどんな収益になるか。「個客」としての横軸が、縦軸の事業とそれぞれ交わるところにユニークポイントがあり、マネタイズされる事業モデルが考えられます。これが金融専業や不動産専業の企業にはできない、当社ならではの連邦活動の事業モデル、ということになります。財務戦略についても現中期計画で始めたバランスシートコントロールをさらにレベルアップさせていきますが、特にお伝えしたいのは株主還元についてです。フェーズⅠは不動産開発投資を開始する前の段階として、キャッシュアロケーションの中で当社がまだまだ足りていない株主還元への比重を高めながら、資本効率の改善を進めます。フェーズⅡ後半からは投資が始まる予定ですが、営業キャッシュ・フローは利益1,000億円に向かい成長するなかで順調に拡大するため、資産入替えなどの手段を講じながら、株主還元強化を継続していきます。
豊かな未来と持続可能な社会の実現に向けて
当社は、企業活動を通じて社会課題解決に貢献し、豊かな未来と持続可能な社会の実現を支えるべく、サステナビリティへの取り組みを進めています。マテリアリティとして「人・地域をつなぐ」「持続可能な環境・社会をつなぐ」、また2023年度は「従業員満足度の向上」だったものを2024年度から「ひとの力の最大化」へ変更し、さらに「グループガバナンス・コミュニケーション」を新たに加えた4つを掲げ、さまざまな取り組みを展開しています。次期中期計画では、百貨店、金融、不動産、その他関連の4つの縦の事業戦略それぞれを、4つのマテリアリティとリンケージさせながらKPIをつくり運用していく、というあたらしい進め方を計画しています。発信と対話について、私はステークホルダーの皆さまとの対話を何より大事にしています。例えば従来の当社ではなかなか進められなかった投資家の皆さまとの対話の機会について、サステナビリティ説明会という新たな対話の場を定例化しました。出席は私だけでなく、サステナビリティを所管するCAO(チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー)、また経営の執行を監督する立場から社外取締役、時には従業員の代表も加わってさまざまな登壇者と共に発信、対話を行っています。

この従業員との関係も、私にとって重要なテーマです。対話の例を挙げると、課長相当級以上の社員と座談会形式で私との対話の時間を設けています。私がCEOとなった2021年に首都圏で始めて以降、2022年は地域や関連会社へも拡大、2024年7月までで延べ198回、315時間、3,488人もの従業員と対話してきました。戦略だけでなく仕事のうえでのさまざまな想いや疑問について直接私と話す重要なコミュニケーションの場としています。経営がここまで従業員とのコミュニケーションに時間を割いてでも一人一人が自ら考え、動き、成果を上げる「きっかけ」にしています。想定を上回るスピードで中期計画の実績が上がっていることも、その裏付けだと思います。従業員との関係、ということで言うと、これから当社が“個客業”へ向かい、実現するために大切なのは企業理念にもあるように、「ひとの力」=従業員です。私は経営としてこの「ひとの力」をいかに最大限に引き出し続けることができるか、常に頭に置きながら進めています。その土台として、従業員の心身の健康、ならびに安全が不可欠です。
三越伊勢丹グループでは、2023年度にグループ労働組合との共同宣言「安心して働くことのできる職場環境づくり」の発信をはじめとして、全ての従業員や一緒に働く仲間が、安全に就業し、心身の健康を保持・増進するための環境づくりに、積極的、かつ継続的に取り組んでいます。今後もこのような「ひとの力」を引き出すための施策を継続的に行うことで、企業理念で掲げるビジョンを「ひとの力」で実現していきたいと考えています。最後に私自身の信条として、自らの倫理観と正義感にのっとり、利害関係などによって偏ることなく、全てのステークホルダーの皆さまにバランスの良い経営を行っていく所存です。そして、全てのステークホルダーの皆さまに当社のファンになっていただけるよう、情報発信やコミュニケーションの在り方、さらなる飛躍に向けたチャレンジの姿勢、夢をお届けする役割、社会への価値提供などについて、常に意識しながら事業に取り組み、企業価値の向上を目指していきます。これからの三越伊勢丹グループの発展にご期待いただき、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。


